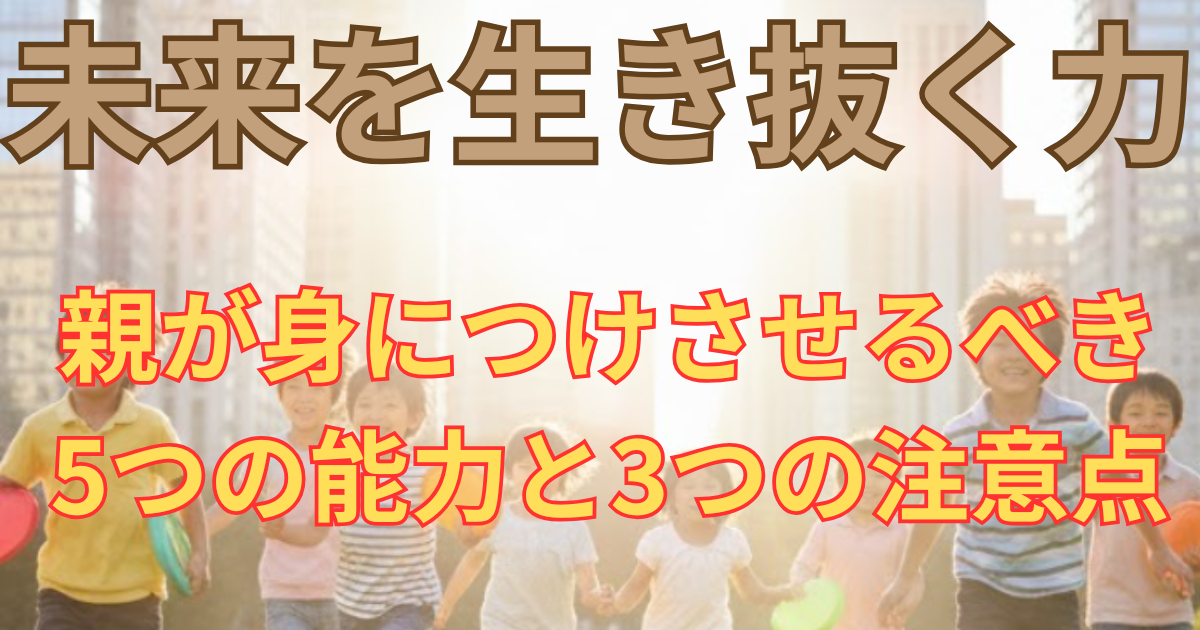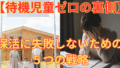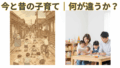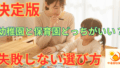【未来を生き抜く力】これからの社会を支える子どもたちへ|今、親が身につけさせるべき5つの能力と3つの注意点
今回は、「【未来を生き抜く力】親が身につけさせるべき5つの能力と3つの注意点」についてご紹介します。
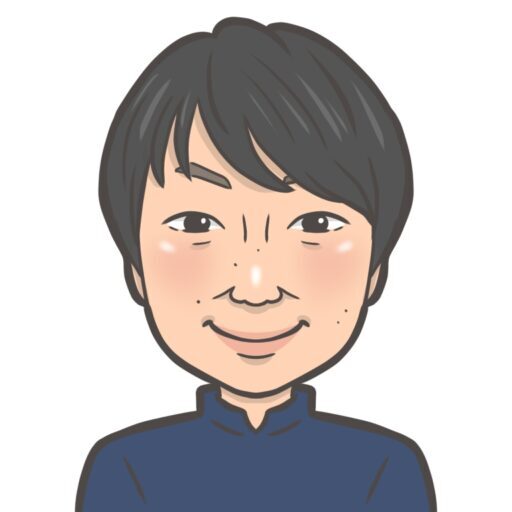
私は、東京都江戸川区の葛西エリアで、中葛西幼保園を20年以上運営しております。
今回は、これからの未来を支えていく子どもたちに焦点をあてて、色々と検討していこうと思います。
変化の時代を生きる子どもたちに必要な羅針盤

これからの未来を支えていく子どもたち①
私たちが生きる現代は、AI(人工知能)の進化、グローバル化、気候変動など、予測不可能な速さで社会構造が変化しています。
大人になった時、子どもたちが直面する社会は、私たちの想像をはるかに超えたものになるでしょう。
従来の「知識の詰め込み」や「正解主義」の教育だけでは、変化の波を乗りこなすことは困難です。
今回は、これからの社会で不可欠となる能力を具体的に解説し、その能力を育むために親や教育者が今すぐ実践すべき「5つの育成ポイント」と「3つの注意点」を、分かりやすくご紹介します。
未来の社会で不可欠となる5つの能力

これからの未来を支えていく子どもたち②
知識やスキルは古くなりますが、これらの能力は時代を超えて子どもの土台となり、生きる力を育みます。
複雑な問題を解決する「クリティカル・シンキング(批判的思考力)」
AIが一般的なタスクや情報整理を担う時代において、人間が求められるのは、
- 「AIが出した答えが本当に正しいか?」
- 「この情報には裏付けがあるか?」
と問いを立てる力です。
求められること
- 情報を鵜呑みにせず、多角的な視点から論理的に分析し、本質を見抜く力。
- 感情論ではなく、事実に基づいた建設的な議論を行う能力。
家庭での育成
「なぜそう思うの?」と頻繁に問いかける習慣をつけましょう。
ニュースや家族会議の場で、子どもに「あなたの意見」とその「理由」を言わせる機会を作ります。
変化に対応し、前進する「レジリエンス(精神的回復力)」
将来は、不確実性に満ちています。
一度の失敗や挫折で立ち止まってしまわず、そこから学び、再び立ち上がれる「心のしなやかさ」こそが、困難を乗り越える鍵となります。
求められること
- 失敗を恐れず挑戦する意欲。
- 逆境を成長の機会と捉え、乗り越えるためのポジティブな解決策を自ら見出す力。
家庭での育成
失敗したときに「ドンマイ、次があるよ」で終わらせず、「どうすれば次はうまくいくかな?一緒に考えてみよう」とプロセスを重視する声かけをします。
親自身が失敗談を話し、乗り越える姿を見せることも重要です。
異文化を理解し、協働する「グローバル・コンピテンス(異文化能力)」
人種、宗教、価値観が異なる人々との協働は、社会のあらゆる場面で必須となります。
多様性を認め、違いを力に変えるコミュニケーション能力が求められます。
求められること
- 異なる文化や背景を持つ人々に敬意を払い、共通の目標に向かって協力し合える能力。
- 外国語能力はもちろん、非言語的なコミュニケーションへの感度も含まれます。
家庭での育成
多様な価値観に触れる機会(国際交流イベント、異文化に関する書籍やドキュメンタリーなど)を提供します。
「自分の常識は世界の常識ではない」という認識を幼い頃から持たせましょう。
自身で課題を見つけ、行動する「主体性(エージェンシー)」
与えられた課題をこなすだけでなく、「今、社会に必要なことは何か」「自分は何ができるか」を自ら問い、行動を起こす力が求められます。これを「エージェンシー(Agency)」と呼びます。
求められること
- 受動的ではなく、能動的に学習や活動に取り組む姿勢。
- 他者や社会に良い影響を与えるために、率先して行動する勇気。
家庭での育成
子ども自身の「やりたい」という気持ちを尊重し、できるだけ口出しをせずに見守ります。
習い事や進路など、重要な選択を子ども自身にさせ、「自分で決める責任」を教えましょう。
感情を認識し、他者に配慮する「社会的・情動的スキル(SEL)」
どんなにテクノロジーが進歩しても、最後は人と人との信頼関係が社会を動かします。
自分の感情を理解し、相手の気持ちを推し量る「EQ(心の知能指数)」が重要になります。
求められること
- 自己肯定感を持ちながら、衝動的な感情をコントロールできる力。
- 他者の立場になって考え、共感し、適切なコミュニケーションを図る力。
家庭での育成
感情を言葉で表現する練習をします。
「今、あなたは〇〇と感じているんだね」と、親が子どもの感情を言語化して返すことで、自己理解を助けます。
親や教育者が今すぐ変えるべき3つの注意点

これからの未来を支えていく子どもたち③
これらの未来の能力を育てるためには、私たち大人が、従来の子育てや教育の常識を見直す必要があります。
「子どもの時間を奪う過保護・過干渉」を避ける
親が先回りして問題解決をしたり、予定を詰め込みすぎたりすることは、子どもの主体性とレジリエンスを奪います。
注意点
「失敗させたくない」「置いていかれたくない」という親の不安から、子どものスケジュールを管理しすぎないようにしましょう。
改善策
子どもに「暇な時間」と「自分で決める自由な時間」を与えましょう。
この時間こそが、自分で遊びや目標を見つけ、クリティカル・シンキングを育む土壌となります。
「成果」ではなく「プロセス」と「努力」に注目するテストの点数や結果だけで評価する声かけは、子どもを「失敗を恐れる子」にしてしまいます。
注意点
「100点で偉いね」ではなく、「難しい問題に粘り強く取り組んだね」と、努力や工夫、成長した点に焦点を当てましょう。
改善策
どんなに小さなことでも、「どうやってそれを思いついたの?」「何か新しい発見はあった?」と、思考の過程について質問しましょう。
これにより、子どもは結果だけでなく、自分の「学び方」そのものに自信を持つようになります。
デジタルリテラシーを「制限」ではなく「活用」の視点で教える
デジタルデバイスは未来の社会を構成するツールであり、単に制限するだけでは、その力を使いこなす能力は育ちません。
注意点
スマホやインターネットを「危険なもの」として一方的に取り上げるのではなく、「強力なツール」として教えましょう。
改善策
-
- 情報の真偽を見極める力(リテラシー)を一緒に学ぶ。
- ゲームや動画視聴だけでなく、プログラミング、情報収集、オンラインでの協働など、デジタルツールを「創造的」に活用する方法を教えます。
- 使用ルールを一方的に決めるのではなく、親子で話し合って決め、「自己管理能力」を育てましょう。
まとめ|親の役割は「未来への橋渡し」

これからの未来を支えていく子どもたち④
これからの社会を支えていく子どもたちにとって、最も必要なのは、「自分の頭で考え、行動し、変化を楽しめる」という内側から湧き出る力です。
私たち親や教育者の役割は、完璧なレールを敷くことではなく、子どもがどんな時代でも自力で立ち、進むことができるよう、心の土台を強くし、未来への羅針盤を与えることです。
今日から、子どもたちの「なぜ?」「やってみたい!」という小さな声を大切にし、結果ではなくプロセスを褒めることから始めてみましょう。
それが、子どもたちの輝かしい未来、そしてより良い社会へとつながる確かな一歩となります。